脳卒中理学療法の理論と技術
第5版
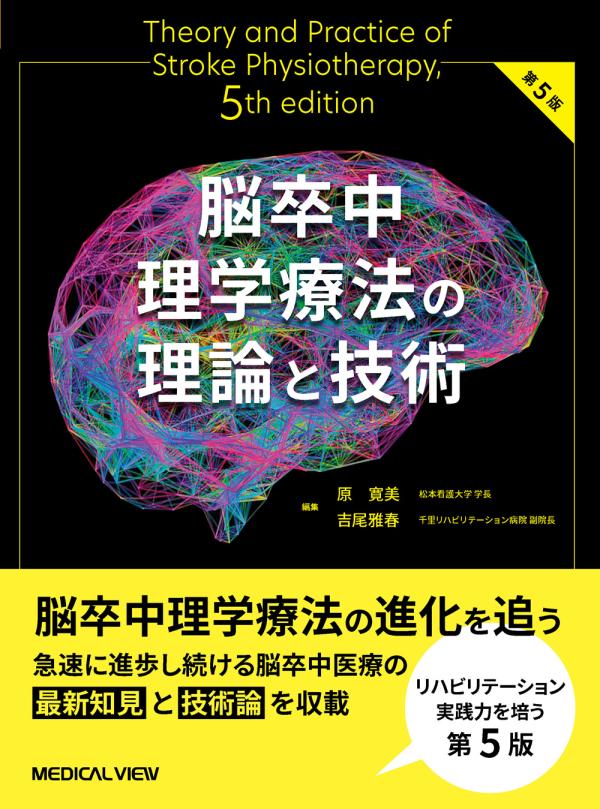
定価 7,700円(税込) (本体7,000円+税)
- B5変型判 552ページ 2色(一部カラー),イラスト480点,写真380点
- 2025年3月21日刊行
- ISBN978-4-7583-2278-2
電子版
序文
本書は2013年に初版を上梓し,その後3年ごとに改訂を重ねてきた。今回第5版の出版となった。今日までの脳卒中医療とリハビリテーションにおける理論的背景と方法論の進化を反映する内容とすべく,毎改訂でブラッシュアップが進められてきた。第4版と比べて以下の内容が主に新しく加筆がされている。
静脈系を含めた脳血管と評価法,脊髄反射に関与するレンショー細胞,心原性脳塞栓症の原因治療のアブレーションと左心耳閉鎖術,塞栓源不明脳塞栓症ESUSにおける植込み型心臓モニターなどの導入,機械的血栓回収術の適用,頭蓋内動脈解離と硬膜動静脈瘻,もやもや病の血行再建術などが,解剖生理学の知識と病態と治療の項に加筆されている。また痙縮の治療でボツリヌス毒素治療の新しいエビデンスとともに,体外衝撃波治療ESWTが加筆されている。さらに脳卒中リハで必須となる栄養管理の項を新しく執筆いただいた。
脳画像からみた脳の障害と理学療法戦略は新しい内容となり,イラストで神経ネットワークを理解できる斬新な項となっている。理論と理学療法では,超急性期からの早期理学療法が新しく執筆され,ER型救急医療体制から開始されるリハが解説されており,発症後のより早期からのリハ介入のモデルが実践を踏まえて執筆されておりインパクトがある。
回復期理学療法の項では,ICFの概念である環境因子として最も重要なのは目の前にいる理学療法士との指摘がされている。喚起すべきスタンスの提言である。歩行訓練のすすめ方では,理論的な背景の説明と下肢装具の活用が詳述されている。CI療法では効果を期待できる導入期として運動麻痺回復ステージ理論に依拠して2nd stageか3rd stageであることが明らかにされている。またロボットを用いた理学療法,機能的電気刺激,小脳系の理学療法,脳卒中の嚥下理学療法の項では,第4版でも掲載していたものを新規の内容として執筆いただいた。ニューロリハビリテーションの項では直近のsystematic reviewを踏まえた記述となっている。脳卒中後の物理療法では電気刺激と振動刺激の理論と有用性について記載されている。この内容以外にも今日までの理論と実臨床に直結する内容が数多く盛り込まれている。
損傷を受けた神経線維は,発症(受傷)後まもなく軸索変性(ワーラー変性)を生じることがわかっている。外傷性脳損傷の重要な病型であるびまん性軸索損傷では,脳内の多くの部位において軸索変性が慢性期にかけて進行し,社会的行動障害などの高次脳機能障害の症状の悪化につながることが解明されてきている。脳卒中における神経損傷も例外ではなく,皮質脊髄路が残存していても,リハ介入有無や経過の中で,急性期から神経線維束の減少・消失が生じる。さらに回復期までのリハにより一旦回復しても,その後の生活期で麻痺肢の不使用となれば,皮質脊髄路の線維束は減退していく。神経組織の可塑性とはいうものの,神経は再生だけではなく,退行的変性も生じることを常に意識して,急性期からのリハ介入と長い生活期を意識したNeuro-protectionにつながるリハ医療の提供が今日求められているといえる。
本書籍が,健康寿命を左右する大きな要因である脳卒中医療とリハビリテーションの必携のテキストとなることを願ってやまない。
2025年3月
原 寛美
吉尾雅春
静脈系を含めた脳血管と評価法,脊髄反射に関与するレンショー細胞,心原性脳塞栓症の原因治療のアブレーションと左心耳閉鎖術,塞栓源不明脳塞栓症ESUSにおける植込み型心臓モニターなどの導入,機械的血栓回収術の適用,頭蓋内動脈解離と硬膜動静脈瘻,もやもや病の血行再建術などが,解剖生理学の知識と病態と治療の項に加筆されている。また痙縮の治療でボツリヌス毒素治療の新しいエビデンスとともに,体外衝撃波治療ESWTが加筆されている。さらに脳卒中リハで必須となる栄養管理の項を新しく執筆いただいた。
脳画像からみた脳の障害と理学療法戦略は新しい内容となり,イラストで神経ネットワークを理解できる斬新な項となっている。理論と理学療法では,超急性期からの早期理学療法が新しく執筆され,ER型救急医療体制から開始されるリハが解説されており,発症後のより早期からのリハ介入のモデルが実践を踏まえて執筆されておりインパクトがある。
回復期理学療法の項では,ICFの概念である環境因子として最も重要なのは目の前にいる理学療法士との指摘がされている。喚起すべきスタンスの提言である。歩行訓練のすすめ方では,理論的な背景の説明と下肢装具の活用が詳述されている。CI療法では効果を期待できる導入期として運動麻痺回復ステージ理論に依拠して2nd stageか3rd stageであることが明らかにされている。またロボットを用いた理学療法,機能的電気刺激,小脳系の理学療法,脳卒中の嚥下理学療法の項では,第4版でも掲載していたものを新規の内容として執筆いただいた。ニューロリハビリテーションの項では直近のsystematic reviewを踏まえた記述となっている。脳卒中後の物理療法では電気刺激と振動刺激の理論と有用性について記載されている。この内容以外にも今日までの理論と実臨床に直結する内容が数多く盛り込まれている。
損傷を受けた神経線維は,発症(受傷)後まもなく軸索変性(ワーラー変性)を生じることがわかっている。外傷性脳損傷の重要な病型であるびまん性軸索損傷では,脳内の多くの部位において軸索変性が慢性期にかけて進行し,社会的行動障害などの高次脳機能障害の症状の悪化につながることが解明されてきている。脳卒中における神経損傷も例外ではなく,皮質脊髄路が残存していても,リハ介入有無や経過の中で,急性期から神経線維束の減少・消失が生じる。さらに回復期までのリハにより一旦回復しても,その後の生活期で麻痺肢の不使用となれば,皮質脊髄路の線維束は減退していく。神経組織の可塑性とはいうものの,神経は再生だけではなく,退行的変性も生じることを常に意識して,急性期からのリハ介入と長い生活期を意識したNeuro-protectionにつながるリハ医療の提供が今日求められているといえる。
本書籍が,健康寿命を左右する大きな要因である脳卒中医療とリハビリテーションの必携のテキストとなることを願ってやまない。
2025年3月
原 寛美
吉尾雅春
全文表示する
閉じる
目次
Ⅰ 解剖生理学の知識
神経系の概観 渡辺雅彦
神経系の解剖学的構成
脳・脊髄の構造と機能 渡辺雅彦
大脳
大脳皮質
海馬
扁桃体
大脳基底核
大脳のその他の構造
間脳
視床
視床上部
視床下部
中脳
橋
延髄
小脳
脊髄
神経組織学 渡辺雅彦
ニューロンの基本構造
シナプスの基本構造
ニューロンの細胞体
樹状突起
軸索
神経伝達物質
受容体
シナプス可塑性
脳の血管 中村 元
はじめに
脳血管の構造
脳の血管:動脈
各種脳血管:静脈
正常変異(破格)
脳血流量の調節
脳血管や脳血流の評価法
疾患との関連
おわりに
Ⅱ 脳卒中の病態と治療
脳卒中の原因と病態 溝口忠孝,岡田 靖
脳卒中の病型分類
虚血性脳卒中
脳出血
くも膜下出血
脳卒中のチーム医療と医療連携
脳卒中の内科的治療 湯浅浩之
はじめに
脳卒中の病態
脳卒中全般の一次予防
脳卒中急性期とは
脳梗塞の病型分類
脳梗塞超急性期(発症4.5時間以内)の診療-救急外来にて
rt-PA治療
機械的血栓回収療法
脳梗塞急性期の治療-急性期病院の病棟にて
脳梗塞慢性期の治療(二次予防)-外来にて
脳出血の内科的治療
おわりに
脳卒中に対する外科治療 千田光平,小笠原邦昭
はじめに
高血圧性脳内出血
脳動脈瘤
頭蓋内動脈解離
脳動静脈奇形
硬膜動静脈瘻
虚血性脳卒中
おわりに
脳卒中の反復性経頭蓋磁気刺激治療rTMSとボツリヌス治療 原 貴敏,安保雅博
はじめに
経頭蓋磁気刺激療法(TMS)とは
経頭蓋磁気刺激療法のリハへの応用
ボツリヌス療法(BoNT-A療法)
おわりに
急性期から開始する脳卒中リハビリテーションの理論とリスク管理 原 寛美
はじめに
なぜ急性期からのリハビリテーションの開始が必要なのか?
運動麻痺回復のメカニズムに依拠したステージ理論( 3 つの回復ステージ)
随意運動の2 つの運動制御系:外側運動制御系と内側運動制御系
運動麻痺の回復を阻害するもの-ワーラー変性と痙縮-
回復ステージ別のリハビリテーションプログラム
ステージ理論に依拠したリハビリテーションプログラムを進めた症例の提示
急性期リハビリテーションにおけるリスク管理
Stroke Unit(SU)における早期離床効果
早期離床の実際
急性期脳卒中におけるベッドサイドリハビリテーション(離床)の方法
まとめ
脳卒中治療・リハビリテーションにおける栄養管理 角田 亘
栄養管理の意義
栄養学の基礎
栄養状態の評価
栄養投与の方法
投与すべき栄養量など
栄養管理の実際
Ⅲ 評価の知識
ADLと総合評価 奥山夕子
脳卒中の障害構造と評価
評価の目的
ADL評価
総合評価
運動機能検査 髙見彰淑
運動機能障害の指標
基本動作能力および体幹を含む姿勢障害の評価
筋緊張の評価
関節可動域測定
筋力検査
運動失調の検査
バランス検査
移乗・移動能力評価
Pushingの評価
上肢機能検査
脳卒中患者の姿勢バランスのみかた
高次脳機能検査 網本 和,渡辺 学
高次脳機能検査の準備 網本 和
全般性認知機能検査
高次運動機能障害の検査 渡辺 学
動作(歩行)分析 大畑光司
動作分析
動作分析の基礎知識
動作,歩行評価の実際
まとめ
脳画像からみた脳の障害と理学療法戦略 吉尾雅春
はじめに
脳画像をみる前に
脳画像からみた脳の障害と理学療法戦略の実例
おわりに
Ⅳ 理論と理学療法
超急性期からの早期理学療法 岩田健太郎,前川侑宏
はじめに
脳卒中急性期におけるER型救急医療と理学療法士の役割
脳卒中における早期理学療法のエビデンス
脳卒中急性期における早期離床
運動機能障害への理学療法
歩行障害への理学療法
早期理学療法の実際-ERにおける脳卒中患者への理学療法士の役割
病態別アプローチ(予後予測とリスク管理)
離床基準と中止基準
早期理学療法と多職種連携
今後の展望
回復期の理学療法で留意すべき事項 吉尾雅春
はじめに
最前線にいることを忘れない
根拠をもって課題に取り組む
チームワーカーとしての責任を全うする
安全管理に責任をもつ
生活に向けて具体的なアプローチを心掛ける
おわりに
歩行練習のすすめ方 増田知子
はじめに
中枢神経系の変化からみた歩行練習のあり方
歩行練習進行の主柱
歩行に関わる機能と障害の理解
歩行練習のエビデンス
下肢装具の活用
後方介助歩行の意義・目的
KAFOからの離脱
症例紹介
移動手段としての歩行の再建
ロボットを用いた理学療法 大畑光司
はじめに
歩行再建に求められる前提条件
下肢機能に対する通常の歩行トレーニング
リハビリテーションロボットの開発とその問題
リハビリテーションロボットの背景理論の再構築
現状の歩行リハビリテーションロボット
まとめ
脳の可塑性と運動療法 森岡 周
脳損傷後の機能回復メカニズム
脳の可塑性の手続き-動物実験から-
脳の可塑性の手続き-ヒトを対象にした脳イメージング研究から-
脳卒中後の運動機能回復に影響を与える要因
脳の可塑性をもたらす運動学習プロセス
CI療法 佐野恭子
CI療法とは
CI療法の理論的背景
CI療法の実際
CI療法の可能性
機能的電気刺激 久保田雅史
はじめに
機能的電気神経刺激の理論
機能的電気神経刺激療法の実際
姿勢定位と空間認知の障害と理学療法 阿部浩明
空間認知と垂直および正中正面判断の障害
半側空間無視の姿勢異常と空間認知障害
脳卒中後の特徴的姿定位障害と空間認知-contraversive pushing(pushing)
Lateropulsion
小脳系の理学療法 廣谷和香
小脳は何をしているのか
病態整理をするうえで必要な知識
小脳障害の臨床症状
小脳障害の評価
小脳障害の理学療法
症例提示
ニューロリハビリテーション 松田雅弘
ニューロリハビリテーションの幕開け
ニューロリハビリテーションの基盤となる理論的背景
ニューロリハビリテーションの発展に寄与した脳機能画像分析
ニューロリハビリテーションの概念を用いたリハビリテーションの展開
BMIのリハビリテーション
再生医療とリハビリテーション
電気刺激療法
複数の手法を用いた併用療法の実際
ニューロリハビリテーションの今後
脳卒中の嚥下理学療法 久保高明
脳卒中と摂食嚥下障害
摂食嚥下とは
摂食嚥下障害の理学療法評価
摂食嚥下障害の理学療法
脳卒中後痙縮のメカニズムと治療 山口智史
はじめに
痙縮の定義
痙縮の疫学
痙縮の発生メカニズム
痙縮の病態
痙性運動障害
痙縮の評価
痙縮の治療
痙縮に対する理学療法の実践
脳卒中後の物理療法 生野公貴
電気刺激療法
脳卒中後運動障害の病態
上肢に対する電気刺激療法
下肢に対する電気刺激療法
振動刺激療法
神経系の概観 渡辺雅彦
神経系の解剖学的構成
脳・脊髄の構造と機能 渡辺雅彦
大脳
大脳皮質
海馬
扁桃体
大脳基底核
大脳のその他の構造
間脳
視床
視床上部
視床下部
中脳
橋
延髄
小脳
脊髄
神経組織学 渡辺雅彦
ニューロンの基本構造
シナプスの基本構造
ニューロンの細胞体
樹状突起
軸索
神経伝達物質
受容体
シナプス可塑性
脳の血管 中村 元
はじめに
脳血管の構造
脳の血管:動脈
各種脳血管:静脈
正常変異(破格)
脳血流量の調節
脳血管や脳血流の評価法
疾患との関連
おわりに
Ⅱ 脳卒中の病態と治療
脳卒中の原因と病態 溝口忠孝,岡田 靖
脳卒中の病型分類
虚血性脳卒中
脳出血
くも膜下出血
脳卒中のチーム医療と医療連携
脳卒中の内科的治療 湯浅浩之
はじめに
脳卒中の病態
脳卒中全般の一次予防
脳卒中急性期とは
脳梗塞の病型分類
脳梗塞超急性期(発症4.5時間以内)の診療-救急外来にて
rt-PA治療
機械的血栓回収療法
脳梗塞急性期の治療-急性期病院の病棟にて
脳梗塞慢性期の治療(二次予防)-外来にて
脳出血の内科的治療
おわりに
脳卒中に対する外科治療 千田光平,小笠原邦昭
はじめに
高血圧性脳内出血
脳動脈瘤
頭蓋内動脈解離
脳動静脈奇形
硬膜動静脈瘻
虚血性脳卒中
おわりに
脳卒中の反復性経頭蓋磁気刺激治療rTMSとボツリヌス治療 原 貴敏,安保雅博
はじめに
経頭蓋磁気刺激療法(TMS)とは
経頭蓋磁気刺激療法のリハへの応用
ボツリヌス療法(BoNT-A療法)
おわりに
急性期から開始する脳卒中リハビリテーションの理論とリスク管理 原 寛美
はじめに
なぜ急性期からのリハビリテーションの開始が必要なのか?
運動麻痺回復のメカニズムに依拠したステージ理論( 3 つの回復ステージ)
随意運動の2 つの運動制御系:外側運動制御系と内側運動制御系
運動麻痺の回復を阻害するもの-ワーラー変性と痙縮-
回復ステージ別のリハビリテーションプログラム
ステージ理論に依拠したリハビリテーションプログラムを進めた症例の提示
急性期リハビリテーションにおけるリスク管理
Stroke Unit(SU)における早期離床効果
早期離床の実際
急性期脳卒中におけるベッドサイドリハビリテーション(離床)の方法
まとめ
脳卒中治療・リハビリテーションにおける栄養管理 角田 亘
栄養管理の意義
栄養学の基礎
栄養状態の評価
栄養投与の方法
投与すべき栄養量など
栄養管理の実際
Ⅲ 評価の知識
ADLと総合評価 奥山夕子
脳卒中の障害構造と評価
評価の目的
ADL評価
総合評価
運動機能検査 髙見彰淑
運動機能障害の指標
基本動作能力および体幹を含む姿勢障害の評価
筋緊張の評価
関節可動域測定
筋力検査
運動失調の検査
バランス検査
移乗・移動能力評価
Pushingの評価
上肢機能検査
脳卒中患者の姿勢バランスのみかた
高次脳機能検査 網本 和,渡辺 学
高次脳機能検査の準備 網本 和
全般性認知機能検査
高次運動機能障害の検査 渡辺 学
動作(歩行)分析 大畑光司
動作分析
動作分析の基礎知識
動作,歩行評価の実際
まとめ
脳画像からみた脳の障害と理学療法戦略 吉尾雅春
はじめに
脳画像をみる前に
脳画像からみた脳の障害と理学療法戦略の実例
おわりに
Ⅳ 理論と理学療法
超急性期からの早期理学療法 岩田健太郎,前川侑宏
はじめに
脳卒中急性期におけるER型救急医療と理学療法士の役割
脳卒中における早期理学療法のエビデンス
脳卒中急性期における早期離床
運動機能障害への理学療法
歩行障害への理学療法
早期理学療法の実際-ERにおける脳卒中患者への理学療法士の役割
病態別アプローチ(予後予測とリスク管理)
離床基準と中止基準
早期理学療法と多職種連携
今後の展望
回復期の理学療法で留意すべき事項 吉尾雅春
はじめに
最前線にいることを忘れない
根拠をもって課題に取り組む
チームワーカーとしての責任を全うする
安全管理に責任をもつ
生活に向けて具体的なアプローチを心掛ける
おわりに
歩行練習のすすめ方 増田知子
はじめに
中枢神経系の変化からみた歩行練習のあり方
歩行練習進行の主柱
歩行に関わる機能と障害の理解
歩行練習のエビデンス
下肢装具の活用
後方介助歩行の意義・目的
KAFOからの離脱
症例紹介
移動手段としての歩行の再建
ロボットを用いた理学療法 大畑光司
はじめに
歩行再建に求められる前提条件
下肢機能に対する通常の歩行トレーニング
リハビリテーションロボットの開発とその問題
リハビリテーションロボットの背景理論の再構築
現状の歩行リハビリテーションロボット
まとめ
脳の可塑性と運動療法 森岡 周
脳損傷後の機能回復メカニズム
脳の可塑性の手続き-動物実験から-
脳の可塑性の手続き-ヒトを対象にした脳イメージング研究から-
脳卒中後の運動機能回復に影響を与える要因
脳の可塑性をもたらす運動学習プロセス
CI療法 佐野恭子
CI療法とは
CI療法の理論的背景
CI療法の実際
CI療法の可能性
機能的電気刺激 久保田雅史
はじめに
機能的電気神経刺激の理論
機能的電気神経刺激療法の実際
姿勢定位と空間認知の障害と理学療法 阿部浩明
空間認知と垂直および正中正面判断の障害
半側空間無視の姿勢異常と空間認知障害
脳卒中後の特徴的姿定位障害と空間認知-contraversive pushing(pushing)
Lateropulsion
小脳系の理学療法 廣谷和香
小脳は何をしているのか
病態整理をするうえで必要な知識
小脳障害の臨床症状
小脳障害の評価
小脳障害の理学療法
症例提示
ニューロリハビリテーション 松田雅弘
ニューロリハビリテーションの幕開け
ニューロリハビリテーションの基盤となる理論的背景
ニューロリハビリテーションの発展に寄与した脳機能画像分析
ニューロリハビリテーションの概念を用いたリハビリテーションの展開
BMIのリハビリテーション
再生医療とリハビリテーション
電気刺激療法
複数の手法を用いた併用療法の実際
ニューロリハビリテーションの今後
脳卒中の嚥下理学療法 久保高明
脳卒中と摂食嚥下障害
摂食嚥下とは
摂食嚥下障害の理学療法評価
摂食嚥下障害の理学療法
脳卒中後痙縮のメカニズムと治療 山口智史
はじめに
痙縮の定義
痙縮の疫学
痙縮の発生メカニズム
痙縮の病態
痙性運動障害
痙縮の評価
痙縮の治療
痙縮に対する理学療法の実践
脳卒中後の物理療法 生野公貴
電気刺激療法
脳卒中後運動障害の病態
上肢に対する電気刺激療法
下肢に対する電気刺激療法
振動刺激療法
全文表示する
閉じる
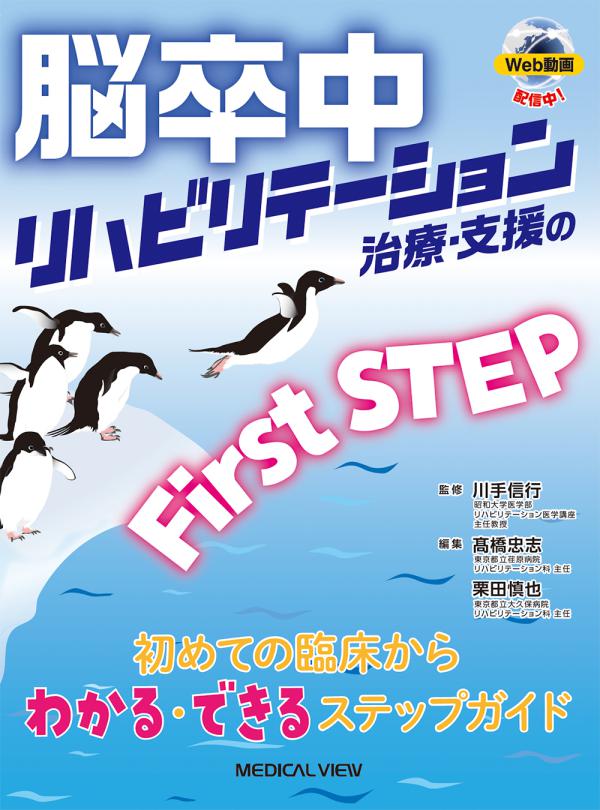
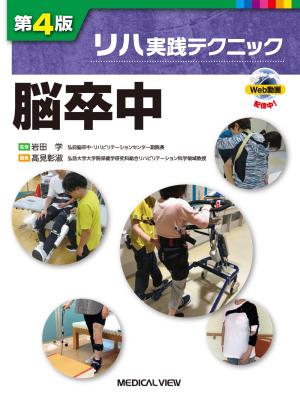
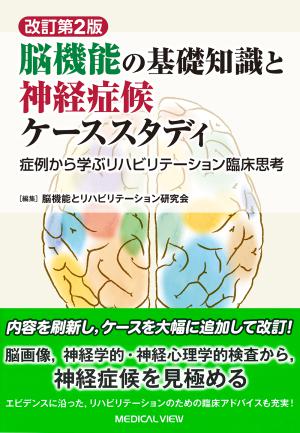
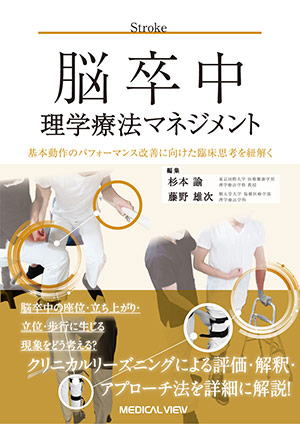

エビデンスに基づく治療のために。日進月歩の脳卒中医療における最新の理論と技術を集約!
進化している脳卒中医療とリハビリテーション医学・医療の知見を収載して,『脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕』に合わせて内容のアップデートを行った。「栄養管理」「機能的電気刺激」の項を新規に設けるとともに,一部項目を刷新,Ⅱ章「病態と治療」も最新の治療トレンドを盛り込んだ。“エビデンスに基づく治療理論を,技術として臨床に導入する”という初版からのコンセプトはそのままに,最新ガイドラインに対応する充実の第5版,脳卒中リハビリテーションに関わる医療従事者必携の一冊。