画像で究める認知症
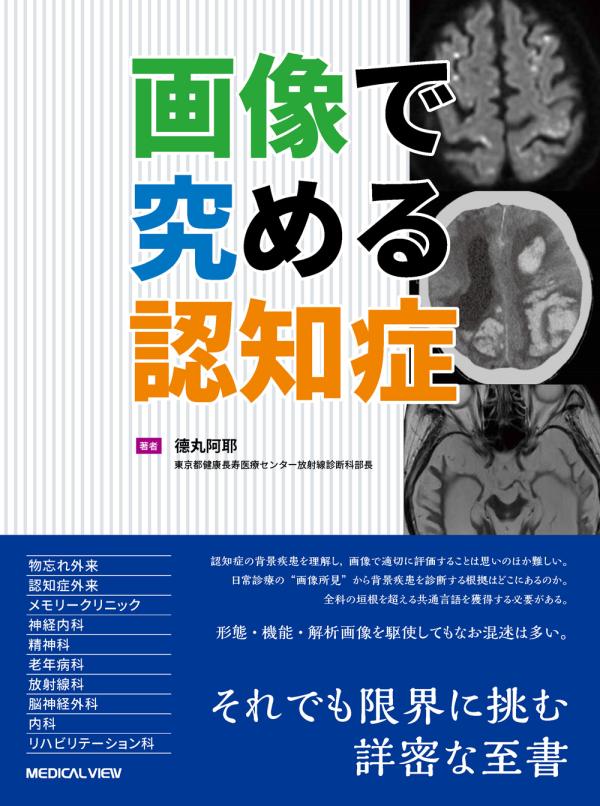
定価 9,900円(税込) (本体9,000円+税)
- B5変型判 320ページ オールカラー,イラスト10点,写真220点
- 2025年3月17日刊行
- ISBN978-4-7583-2113-6
電子版
序文
推薦の辞
本書を認知症診断・診療に携わるすべての医師に推薦します。
アルツハイマー病に対する抗アミロイドβ抗体薬が承認され,診療実装が始まり1年が経過したところで本書は刊行されます。脳MRIは抗アミロイドβ抗体薬診療において,対象候補患者の鑑別診断,治療可否の要件確認,安全性のモニタリングと,きわめて重要な位置を占める検査であり,本書にはその手順や要点が詳細に解説されています。また,抗アミロイドβ抗体薬治療の対象とならない方々の鑑別診断や合併病理の評価も非常に重要ですが,本書はその診療のよき道標となることでしょう。
本書は脳MRIを中心とする認知症画像診断の実践的なテキストとして,国内外でも類をみない充実した内容となっています。豊富な症例画像とともに,鑑別の要点が図表として簡潔にまとめられており,理解を促します。また,参考となる基礎知識や関連事項がNOTEやCOLUMNとして添えられており,楽しく読み進めながら理解を深めることができます。德丸阿耶先生の読影は,オーソドックスな系統的読影と豊富な文献的知識に裏付けられているだけでなく,独自の観察眼と画像病理相関によって確認した症例が多数提示・解説されています。アルツハイマー病との鑑別が必要なレビー小体型認知症,前頭側頭葉変性症に加え,特に高齢者タウオパチーに多くの分量を割いていることは本書の白眉をなす点だと思います。また,第V章「拡散強調像が鍵となる疾患」も類書に例を見ない詳細な記載で熟読に値します。
私が初めて德丸先生の謦咳に接する機会を得たのは約20年前ですが,患者さんの利き手や性別だけでなく,さまざまな背景をあたかも見てきたが如く言い当てられることに驚かされました。それは,卓越した観察眼で相手の職業や出身などを言い当てる,名探偵シャーロック・ホームズを彷彿とさせるものでした。医師でもあった作者コナン・ドイルが,「花婿失踪事件(A Case of Identity)」のなかでホームズに語らせた,
“ Not invisible but unnoticed, Watson. You did not know where to look, and so you missed all that was important.”
という言葉は,まさに德丸先生の画像診断に当てはまる言葉だと思います。その一端は,第Ⅰ章「鑑別診断の基本」のなかで,画像を「隅から隅までみる」ことの大切さに言及されていることからもわかります。そして,德丸先生はその先に何をみようとしているのか? それが本書を紐解くと明らかになりますが,“すべては患者さんのよりよい診断・治療・生活のために活かされなければならない”という信念に貫かれています。
德丸先生のレポートは常に担当臨床医のアクションを促すものですが,本書はそのような神経放射線診断医としての德丸先生の矜持に触れることのできる,貴重な体験をもたらしてくれます。専門的な診断医を目指す若い先生方には特に“座右の書”として熟読していただきたく,本書を推薦いたします。
2025年2月
東京都健康長寿医療センター研究所 神経画像研究チーム
石井賢二
------------------
序
七十七歳で喜寿,八十歳は傘寿,八十八歳では米寿,九十歳卆寿,九十九歳白寿,百歳百寿と,齢を重ねることを私達の社会は常に寿いできました。古い時代の東北の地では,認知症は二度童子(にどわらし)ともよばれていたと聞きます。二度童子:ふたたびの子供時代がそこにある,というその言葉からは,齢を重ねることや認知症であることを,人々が受容してきた暖かさやおおらかさも感じとれるように思います。家族や地域社会のありかたも大きく変容し続ける2025年現在,わが国では百寿者が9万5千人を越えました。未曾有の超高齢化社会が現実となり,認知症と真摯に向き合うことが喫緊の課題となっています。世界を見渡しても,Alzheimer’s Disease International(https://www.alzint.org/)によれば,2020年に認知症は5,500万人を数え(これは少なく見積もった数字といえる),3秒ごとに世界のどこかで新たに1人が認知症となり,認知症罹患者は20年ごとに2倍のスピードで増加し,2050年には1億3,900万人が認知症になると試算し,今こそ社会を挙げて認知症に取り組むべきであると警鐘を鳴らしています。
さて,どのような時代が巡ってきたとしても,認知症患者一人一人が適切な医療,看護,介護を選択し,“より豊かに生き抜く”ための第一歩は,“あなたの認知症,私の認知症の原因は何か”を知ることにあると思います。まず,病因を突き止め,その病因に対処する道筋を立てることが大事だということは,ほかのどのような病とも異なることはないはずです。
今,認知症画像診断は明確な転換期を迎えています。2021年6月に米国食品医薬品局(US Food & Drug Administration:FDA)は,アルツハイマー病の主病因の1つであるアミロイドβ(Aβ)を標的とする抗Aβ抗体薬アデュカヌマブを承認しました。その際には,治験結果の解釈,治験段階のプライマリーエンドポイントを満たしているのかどうか,適応患者選択はいかにあるべきか,ARIA(amyloid-related imaging abnormalities(第Ⅲ章1 アルツハイマー病,p.32参照)をはじめとする副作用評価のあり方など大きな議論を巻き起こし,それらの課題を継続して検討すべきであると銘記しつつの承認でした。その後,わが国においても臨床実装への準備が進み,2025年1月現在,2つの抗Aβ抗体薬が保険収載され,軽度認知障害,アルツハイマー病初期への薬剤投与が始まっています。いよいよ認知症画像診断は,臨床診断の補助あるいは除外(鑑別)の役割に留まらず,疾患修飾薬開発や疾患予防に直接寄与すべき時期に到達し,発症前からごく初期段階での診断バイオマーカー,および疾患修飾薬(治験段階を含む)効能サロゲートマーカーとして客観的,かつ汎用性をもって確立することをも求められています。神経画像への期待は大きく,この重い責任を果たすために精度管理,標準化,汎用性の検証,疾患単位に留まらない疾患横断的な検証などが進められていますが,その第一歩はやはり日常の画像診断にあります。新しい役割を果たすためには,アルツハイマー病一つを取り上げても病因蛋白のAβやタウが脳内に存在することを可視化することが求められるのですが,日常臨床診断でその責務に応えることは容易なことではありません。発症前のアルツハイマー病を,日常臨床で用いるMRIやCTで診断できているのかと問われれば,否と答えざるをえません。しかし,それでも筆者は,発症前診断を視野にいれた診断バイオマーカー,サロゲートマーカーとしての神経画像研究の役割と日常臨床における認知症画像診断は乖離すべきものではなく,それぞれに大切な役割があり,途切れることなく稠密につながっているはずだと信じたい。臨床,看護,介護,行政,患者さん,患者さんのご家族にとって,病態を可視化して提示しうる神経画像の意味はある,そのことをこの原稿を起こすにあたり,改めて一緒に考えていきたいと思っています。
認知症は,私達が生きる過程で得る術,愛し,学び,働くことの原動力となる情動,知能,意欲のいずれもが失われていく過程であり,病態を表すものです。画像診断医は,逆説的ではありますが“認知症という画像診断名はない”と心し,認知症をきたす無数の疾患を客観的画像情報に基づき,できるだけ正確に臨床に結び,病態を明らかにするために目を凝らしています。Aβやタウがみえずとも,日常画像診断の現場では,これからも“普通の”CTやMRIが認知症診断の第一選択です。適切な対処によって臨床症状の改善が望める疾患,ハキム病(特発性正常圧水頭症),代謝性脳症,アミロイドアンギオパチー関連炎症などをまず正しく鑑別し,そのうえで認知症をきたす要因が血管性であるのか,変性性認知症であるのか,そのほかの因子であるのかを見極め,もてるモダリティを駆使し,病期の判断,背景疾患について臨床に役立つ情報を提供することの重要さは,いや増していると実感しています。
認知症を取り巻く課題は多面的です。2017年3月に施行された改正道路交通法により,運転免許更新時一定の交通違反を行った際に警察で行う簡易認知機能検査で「認知症疑い」となった75歳以上の高齢者は,都道府県公安委員会の指示によって認知症であるかどうかの検査,診断を受けることが必要となり,この過程で“画像診断”による判断を求められることも増えました。おのずから社会情勢と深くかかわっていることに驚きます。この一事をとっても,日常臨床で得られる日々の画像情報の積み重ねは,地域で生きる高齢者にどのような社会的サポートが必要か,どのように認知症発症予防,進行抑制をしていくか,認知症,軽度認知障害を社会がどのように受容していくか,適切な医療費配分,社会福祉基盤整備の指針ともなりうるもののように感じています。
筆者は,2005年1月1日に独立行政法人東京都健康長寿医療センター(旧東京都老人医療センター)放射線診断科に赴任し,高齢者画像診断に初めて従事することになったのですが,当初は五里霧中,手も足も出ませんでした。同じ条件でT2強調横断像を撮像しても,40代と80代では,なにしろ黒白のコントラストが異なってみえるのですから! さらには,認知症の患者さんに画像を撮る必要があるのか? 放射線科医が脳の画像を読影するのか? あなたに脳が読めるのか? とまで問われ,受け容れていただくまでに紆余曲折がありました。まず画像を撮っていただくことからお願いし,診断の道筋に神経画像を入れていただくための努力はごく矮小なものでありました。しかし,私達は今日,真に公平に,あるべきバイオマーカー,サロゲートマーカーを提供するために,日常臨床診断機器でもあるMRI,CTと,保険適用の限定,機器の数やスタッフに制限のあるPET,さらには脳脊髄液,血液バイオマーカーなど最先端診断技術を適切に組み合わせ,認知症に対峙する社会インフラを整備する機運のなかにいます。同時に,認知症と向き合うなかでは,「撮る意味があるのか?」と20年前に問われたことにもう一度向き合うことも少なくありません。“知らないでいる選択,診断を受けない選択”もあり,その理由はさまざまですが(そのなかには,個々の経済的な事情も含まれる),それぞれに尊重されるべき場面に直面いたします。公平に画像を提供するとはどういうことなのか,正常とは何かさえ,いまだに考えさせられる日々が続いています。
五里霧中のなか,指針となったのは研修医1年目の東京都立広尾病院放射線科での経験です。そこでは小林 剛先生の下,毎日全員がその日のすべての画像を共有し,議論が交わされていました。小林 剛先生は,責任者として多忙のなか,画像診断を得たすべての患者さんを追跡しておられました。手術があれば手術所見と病理を,剖検があればその記録を確認し,画像に対応され,記録を取っておられたのです。ときを経て,筆者の所属する東京都健康長寿医療センターでは,病理診断科 新井富生先生,神経病理,ブレインバンクの齊藤祐子先生,村山繁雄先生をはじめとする皆さん,PETセンター 石井賢二先生をはじめ研究所の先生方,スタッフの皆さん,臨床各科の先生方,海野 泰技師長をはじめとする放射線科技師の皆さん,看護師,事務方,かかわるあらゆるスタッフの皆様による不断の努力と患者さん,またご家族の尊いお気持ちに支えられ,毎週剖検症例のカンファレンスが行われています。その場所に集い,臨床―画像―病理の連関を学ぶなかで,二次元の黒白の画像は,各々に異なる多面的な様相をみせてくれるようにもなりました。いまだに筆者自身は五里霧中におりますが,本書が日常臨床診断医として,多彩な認知症の背景を読み解くよすがとなるよう,努めたいと考えています。
認知症の画像診断は,読影室の中だけでは完結せず,主治医,臨床心理士,技師,看護師,患者さんとご家族,サポートケアスタッフ,病理医,研究者,かかわるすべての人とともに,画像診断レポートを育てていくことが大事なのではないかと感じています。多くの専門家がかかわる領域であるがゆえに,それぞれのお立場から本書の内容が物足りないとお感じになることがあると思いますが,日常臨床診断からの問いかけであり,今この時点の第一歩と御寛恕いただき,ご教示をいただければ嬉しく存じます。
本書は単著となっていますが,書き進めれば進めるほど,関係するすべての皆さんとの共著であるという思いが深まりました。謝辞を申し述べるべき皆さんは文字どおり枚挙にいとまがなく,個別に挙げることが叶いません。井藤英喜名誉理事長,東京都健康長寿医療センターのすべての皆さん,小さな放射線科に遠方から学びに来てくださった櫻井圭太先生,宮田真里先生をはじめとする次代を担う皆さん,ご教示をいただきお支えいただきました皆さんに,深く感謝を申し上げます。また,Medical View社の井上紘一郎さんには,逡巡し逃げまどう筆者を励まし,形にしていただくためのすべてをサポートしていただきました。お仕事の域を超えた“編集の力”なくして本書は成立しませんでした。心より御礼申し上げます。
2025年睦月
東京都健康長寿医療センター 放射線診断科
德丸阿耶
本書を認知症診断・診療に携わるすべての医師に推薦します。
アルツハイマー病に対する抗アミロイドβ抗体薬が承認され,診療実装が始まり1年が経過したところで本書は刊行されます。脳MRIは抗アミロイドβ抗体薬診療において,対象候補患者の鑑別診断,治療可否の要件確認,安全性のモニタリングと,きわめて重要な位置を占める検査であり,本書にはその手順や要点が詳細に解説されています。また,抗アミロイドβ抗体薬治療の対象とならない方々の鑑別診断や合併病理の評価も非常に重要ですが,本書はその診療のよき道標となることでしょう。
本書は脳MRIを中心とする認知症画像診断の実践的なテキストとして,国内外でも類をみない充実した内容となっています。豊富な症例画像とともに,鑑別の要点が図表として簡潔にまとめられており,理解を促します。また,参考となる基礎知識や関連事項がNOTEやCOLUMNとして添えられており,楽しく読み進めながら理解を深めることができます。德丸阿耶先生の読影は,オーソドックスな系統的読影と豊富な文献的知識に裏付けられているだけでなく,独自の観察眼と画像病理相関によって確認した症例が多数提示・解説されています。アルツハイマー病との鑑別が必要なレビー小体型認知症,前頭側頭葉変性症に加え,特に高齢者タウオパチーに多くの分量を割いていることは本書の白眉をなす点だと思います。また,第V章「拡散強調像が鍵となる疾患」も類書に例を見ない詳細な記載で熟読に値します。
私が初めて德丸先生の謦咳に接する機会を得たのは約20年前ですが,患者さんの利き手や性別だけでなく,さまざまな背景をあたかも見てきたが如く言い当てられることに驚かされました。それは,卓越した観察眼で相手の職業や出身などを言い当てる,名探偵シャーロック・ホームズを彷彿とさせるものでした。医師でもあった作者コナン・ドイルが,「花婿失踪事件(A Case of Identity)」のなかでホームズに語らせた,
“ Not invisible but unnoticed, Watson. You did not know where to look, and so you missed all that was important.”
という言葉は,まさに德丸先生の画像診断に当てはまる言葉だと思います。その一端は,第Ⅰ章「鑑別診断の基本」のなかで,画像を「隅から隅までみる」ことの大切さに言及されていることからもわかります。そして,德丸先生はその先に何をみようとしているのか? それが本書を紐解くと明らかになりますが,“すべては患者さんのよりよい診断・治療・生活のために活かされなければならない”という信念に貫かれています。
德丸先生のレポートは常に担当臨床医のアクションを促すものですが,本書はそのような神経放射線診断医としての德丸先生の矜持に触れることのできる,貴重な体験をもたらしてくれます。専門的な診断医を目指す若い先生方には特に“座右の書”として熟読していただきたく,本書を推薦いたします。
2025年2月
東京都健康長寿医療センター研究所 神経画像研究チーム
石井賢二
------------------
序
七十七歳で喜寿,八十歳は傘寿,八十八歳では米寿,九十歳卆寿,九十九歳白寿,百歳百寿と,齢を重ねることを私達の社会は常に寿いできました。古い時代の東北の地では,認知症は二度童子(にどわらし)ともよばれていたと聞きます。二度童子:ふたたびの子供時代がそこにある,というその言葉からは,齢を重ねることや認知症であることを,人々が受容してきた暖かさやおおらかさも感じとれるように思います。家族や地域社会のありかたも大きく変容し続ける2025年現在,わが国では百寿者が9万5千人を越えました。未曾有の超高齢化社会が現実となり,認知症と真摯に向き合うことが喫緊の課題となっています。世界を見渡しても,Alzheimer’s Disease International(https://www.alzint.org/)によれば,2020年に認知症は5,500万人を数え(これは少なく見積もった数字といえる),3秒ごとに世界のどこかで新たに1人が認知症となり,認知症罹患者は20年ごとに2倍のスピードで増加し,2050年には1億3,900万人が認知症になると試算し,今こそ社会を挙げて認知症に取り組むべきであると警鐘を鳴らしています。
さて,どのような時代が巡ってきたとしても,認知症患者一人一人が適切な医療,看護,介護を選択し,“より豊かに生き抜く”ための第一歩は,“あなたの認知症,私の認知症の原因は何か”を知ることにあると思います。まず,病因を突き止め,その病因に対処する道筋を立てることが大事だということは,ほかのどのような病とも異なることはないはずです。
今,認知症画像診断は明確な転換期を迎えています。2021年6月に米国食品医薬品局(US Food & Drug Administration:FDA)は,アルツハイマー病の主病因の1つであるアミロイドβ(Aβ)を標的とする抗Aβ抗体薬アデュカヌマブを承認しました。その際には,治験結果の解釈,治験段階のプライマリーエンドポイントを満たしているのかどうか,適応患者選択はいかにあるべきか,ARIA(amyloid-related imaging abnormalities(第Ⅲ章1 アルツハイマー病,p.32参照)をはじめとする副作用評価のあり方など大きな議論を巻き起こし,それらの課題を継続して検討すべきであると銘記しつつの承認でした。その後,わが国においても臨床実装への準備が進み,2025年1月現在,2つの抗Aβ抗体薬が保険収載され,軽度認知障害,アルツハイマー病初期への薬剤投与が始まっています。いよいよ認知症画像診断は,臨床診断の補助あるいは除外(鑑別)の役割に留まらず,疾患修飾薬開発や疾患予防に直接寄与すべき時期に到達し,発症前からごく初期段階での診断バイオマーカー,および疾患修飾薬(治験段階を含む)効能サロゲートマーカーとして客観的,かつ汎用性をもって確立することをも求められています。神経画像への期待は大きく,この重い責任を果たすために精度管理,標準化,汎用性の検証,疾患単位に留まらない疾患横断的な検証などが進められていますが,その第一歩はやはり日常の画像診断にあります。新しい役割を果たすためには,アルツハイマー病一つを取り上げても病因蛋白のAβやタウが脳内に存在することを可視化することが求められるのですが,日常臨床診断でその責務に応えることは容易なことではありません。発症前のアルツハイマー病を,日常臨床で用いるMRIやCTで診断できているのかと問われれば,否と答えざるをえません。しかし,それでも筆者は,発症前診断を視野にいれた診断バイオマーカー,サロゲートマーカーとしての神経画像研究の役割と日常臨床における認知症画像診断は乖離すべきものではなく,それぞれに大切な役割があり,途切れることなく稠密につながっているはずだと信じたい。臨床,看護,介護,行政,患者さん,患者さんのご家族にとって,病態を可視化して提示しうる神経画像の意味はある,そのことをこの原稿を起こすにあたり,改めて一緒に考えていきたいと思っています。
認知症は,私達が生きる過程で得る術,愛し,学び,働くことの原動力となる情動,知能,意欲のいずれもが失われていく過程であり,病態を表すものです。画像診断医は,逆説的ではありますが“認知症という画像診断名はない”と心し,認知症をきたす無数の疾患を客観的画像情報に基づき,できるだけ正確に臨床に結び,病態を明らかにするために目を凝らしています。Aβやタウがみえずとも,日常画像診断の現場では,これからも“普通の”CTやMRIが認知症診断の第一選択です。適切な対処によって臨床症状の改善が望める疾患,ハキム病(特発性正常圧水頭症),代謝性脳症,アミロイドアンギオパチー関連炎症などをまず正しく鑑別し,そのうえで認知症をきたす要因が血管性であるのか,変性性認知症であるのか,そのほかの因子であるのかを見極め,もてるモダリティを駆使し,病期の判断,背景疾患について臨床に役立つ情報を提供することの重要さは,いや増していると実感しています。
認知症を取り巻く課題は多面的です。2017年3月に施行された改正道路交通法により,運転免許更新時一定の交通違反を行った際に警察で行う簡易認知機能検査で「認知症疑い」となった75歳以上の高齢者は,都道府県公安委員会の指示によって認知症であるかどうかの検査,診断を受けることが必要となり,この過程で“画像診断”による判断を求められることも増えました。おのずから社会情勢と深くかかわっていることに驚きます。この一事をとっても,日常臨床で得られる日々の画像情報の積み重ねは,地域で生きる高齢者にどのような社会的サポートが必要か,どのように認知症発症予防,進行抑制をしていくか,認知症,軽度認知障害を社会がどのように受容していくか,適切な医療費配分,社会福祉基盤整備の指針ともなりうるもののように感じています。
筆者は,2005年1月1日に独立行政法人東京都健康長寿医療センター(旧東京都老人医療センター)放射線診断科に赴任し,高齢者画像診断に初めて従事することになったのですが,当初は五里霧中,手も足も出ませんでした。同じ条件でT2強調横断像を撮像しても,40代と80代では,なにしろ黒白のコントラストが異なってみえるのですから! さらには,認知症の患者さんに画像を撮る必要があるのか? 放射線科医が脳の画像を読影するのか? あなたに脳が読めるのか? とまで問われ,受け容れていただくまでに紆余曲折がありました。まず画像を撮っていただくことからお願いし,診断の道筋に神経画像を入れていただくための努力はごく矮小なものでありました。しかし,私達は今日,真に公平に,あるべきバイオマーカー,サロゲートマーカーを提供するために,日常臨床診断機器でもあるMRI,CTと,保険適用の限定,機器の数やスタッフに制限のあるPET,さらには脳脊髄液,血液バイオマーカーなど最先端診断技術を適切に組み合わせ,認知症に対峙する社会インフラを整備する機運のなかにいます。同時に,認知症と向き合うなかでは,「撮る意味があるのか?」と20年前に問われたことにもう一度向き合うことも少なくありません。“知らないでいる選択,診断を受けない選択”もあり,その理由はさまざまですが(そのなかには,個々の経済的な事情も含まれる),それぞれに尊重されるべき場面に直面いたします。公平に画像を提供するとはどういうことなのか,正常とは何かさえ,いまだに考えさせられる日々が続いています。
五里霧中のなか,指針となったのは研修医1年目の東京都立広尾病院放射線科での経験です。そこでは小林 剛先生の下,毎日全員がその日のすべての画像を共有し,議論が交わされていました。小林 剛先生は,責任者として多忙のなか,画像診断を得たすべての患者さんを追跡しておられました。手術があれば手術所見と病理を,剖検があればその記録を確認し,画像に対応され,記録を取っておられたのです。ときを経て,筆者の所属する東京都健康長寿医療センターでは,病理診断科 新井富生先生,神経病理,ブレインバンクの齊藤祐子先生,村山繁雄先生をはじめとする皆さん,PETセンター 石井賢二先生をはじめ研究所の先生方,スタッフの皆さん,臨床各科の先生方,海野 泰技師長をはじめとする放射線科技師の皆さん,看護師,事務方,かかわるあらゆるスタッフの皆様による不断の努力と患者さん,またご家族の尊いお気持ちに支えられ,毎週剖検症例のカンファレンスが行われています。その場所に集い,臨床―画像―病理の連関を学ぶなかで,二次元の黒白の画像は,各々に異なる多面的な様相をみせてくれるようにもなりました。いまだに筆者自身は五里霧中におりますが,本書が日常臨床診断医として,多彩な認知症の背景を読み解くよすがとなるよう,努めたいと考えています。
認知症の画像診断は,読影室の中だけでは完結せず,主治医,臨床心理士,技師,看護師,患者さんとご家族,サポートケアスタッフ,病理医,研究者,かかわるすべての人とともに,画像診断レポートを育てていくことが大事なのではないかと感じています。多くの専門家がかかわる領域であるがゆえに,それぞれのお立場から本書の内容が物足りないとお感じになることがあると思いますが,日常臨床診断からの問いかけであり,今この時点の第一歩と御寛恕いただき,ご教示をいただければ嬉しく存じます。
本書は単著となっていますが,書き進めれば進めるほど,関係するすべての皆さんとの共著であるという思いが深まりました。謝辞を申し述べるべき皆さんは文字どおり枚挙にいとまがなく,個別に挙げることが叶いません。井藤英喜名誉理事長,東京都健康長寿医療センターのすべての皆さん,小さな放射線科に遠方から学びに来てくださった櫻井圭太先生,宮田真里先生をはじめとする次代を担う皆さん,ご教示をいただきお支えいただきました皆さんに,深く感謝を申し上げます。また,Medical View社の井上紘一郎さんには,逡巡し逃げまどう筆者を励まし,形にしていただくためのすべてをサポートしていただきました。お仕事の域を超えた“編集の力”なくして本書は成立しませんでした。心より御礼申し上げます。
2025年睦月
東京都健康長寿医療センター 放射線診断科
德丸阿耶
全文表示する
閉じる
目次
第Ⅰ章 鑑別診断の基本
1. 認知症の画像診断とは
認知症という画像診断名は存在しない!
2. 実際に鑑別してみよう
認知症をきたす背景疾患は多種多様
最初の3分で,どこをみる?
どのように脳室拡大を記載する?
片側優位の脳室,脳溝拡大をみたら?
第Ⅱ章 鑑別診断の実際
1. 水頭症
水頭症とは
水頭症の分類
第Ⅲ章 神経変性疾患
1. アルツハイマー病(AD)
はじめに
ADの病因・病態
臨床
分類・遺伝
非定形AD:主たる3タイプ
ADの診断基準
ADの日常画像診断:画像診断過程
早発性AD(EOAD)・若年性ADの画像診断における注意点
非定形ADの画像所見
複合病理の存在を忘れない
MCI段階のADと鑑別すべき疾患とその鑑別点
その他とまとめ
抗Aβ抗体薬実装に際した投与前MRIチェック事項(簡略紹介)
2. Lewy小体型認知症/認知症を伴うパーキンソン病(DLB/PDD)
はじめに
DLBとPDDについて
Lewy小体病の病態
画像と診断
3. 高齢者タウオパチー① 嗜銀顆粒性認知症/嗜銀顆粒病(DG/AGD)
疾患概念
臨床
疫学
画像所見
4. 高齢者タウオパチー② 神経原線維変化型老年期認知症(SD-NFT)/原発性年齢関連タウオパチー(PART)
疾患概念
臨床
画像所見
症例検討
5. 高齢者タウオパチー③ 進行性核上性麻痺(PSP)
はじめに
臨床
画像所見
6. 高齢者タウオパチー④ 大脳皮質基底核変性症(CBD)/ 大脳皮質基底核症候群(CBS)
はじめに
臨床
画像所見
今後の課題
7. 前頭側頭葉変性症(FTLD)
はじめに
疾患概念116
臨床症候の分類
bvFTD,SD,PNFAの画像所見
原発性進行性失語症(PPA)
FTLDの神経病理学的分類
FTLDトピックス
8. 高齢者の海馬硬化症~白くて小さい海馬の背景を探る
はじめに
認知症でやってくる高齢者の海馬硬化症~HS-Agingがある
HS-Agingの背景病理
HS-Agingの臨床
CARTS,LATE
HS-AgingをMRIで診断しましょう
第Ⅳ章 血管性認知症
1. 血管性認知症の多様な病態
はじめに
血管性認知症の診断基準
血管性認知症の分類
一過性全健忘(TGA)
第Ⅴ章 拡散強調像が鍵となる疾患
1. pathognomonicな信号異常が診断の端緒となりうる疾患・病態
はじめに
プリオン病
神経核内封入体病(NIID)
脆弱X関連振戦/ 失調症候群(FXTAS)
Hereditary diffuse leukoencephalopathy with spheroid(HDLS)
第Ⅵ章 積極的鑑別が必要な背景疾患
1. これだけは知っておきたい,その他の重要疾患
はじめに
高齢者の救急:認知症とのかかわり
“これだけは知っておきたい”理由は何か?
N:neoplasm(腫瘍性)
I :intoxication(中毒)
I :infection
M:metabolic(代謝性異常)
A:autoimmune(自己免疫性)
T :trauma(外傷と認知症)
老年期うつ病と認知症
第Ⅶ章 高齢者てんかんと認知症
1. 高齢者のてんかん
はじめに
日常画像診断でなすべきこと
第Ⅷ章 複合病理
1. 認知症の背景には複合的な病態が高率に存在する
はじめに
複合的な背景を診断するステップ
第Ⅸ章 社会とのかかわり~これからの画像診断の役割
1. 生活不活発病(フレイルとサルコペニア)
生活不活発病
フレイル(frailty)
サルコペニア
フレイル・サルコペニアの影響
フレイル・サルコペニアと画像診断
2. 虐待(abuse)
超高齢者社会における重要課題
3. 認知症と交通,運転免許
整備される法改正
4. ごみ屋敷症候群(別名:ディオゲネス症候群),熱中症など
ゴミ屋敷症候群とよばれる所以と背景要因
1. 認知症の画像診断とは
認知症という画像診断名は存在しない!
2. 実際に鑑別してみよう
認知症をきたす背景疾患は多種多様
最初の3分で,どこをみる?
どのように脳室拡大を記載する?
片側優位の脳室,脳溝拡大をみたら?
第Ⅱ章 鑑別診断の実際
1. 水頭症
水頭症とは
水頭症の分類
第Ⅲ章 神経変性疾患
1. アルツハイマー病(AD)
はじめに
ADの病因・病態
臨床
分類・遺伝
非定形AD:主たる3タイプ
ADの診断基準
ADの日常画像診断:画像診断過程
早発性AD(EOAD)・若年性ADの画像診断における注意点
非定形ADの画像所見
複合病理の存在を忘れない
MCI段階のADと鑑別すべき疾患とその鑑別点
その他とまとめ
抗Aβ抗体薬実装に際した投与前MRIチェック事項(簡略紹介)
2. Lewy小体型認知症/認知症を伴うパーキンソン病(DLB/PDD)
はじめに
DLBとPDDについて
Lewy小体病の病態
画像と診断
3. 高齢者タウオパチー① 嗜銀顆粒性認知症/嗜銀顆粒病(DG/AGD)
疾患概念
臨床
疫学
画像所見
4. 高齢者タウオパチー② 神経原線維変化型老年期認知症(SD-NFT)/原発性年齢関連タウオパチー(PART)
疾患概念
臨床
画像所見
症例検討
5. 高齢者タウオパチー③ 進行性核上性麻痺(PSP)
はじめに
臨床
画像所見
6. 高齢者タウオパチー④ 大脳皮質基底核変性症(CBD)/ 大脳皮質基底核症候群(CBS)
はじめに
臨床
画像所見
今後の課題
7. 前頭側頭葉変性症(FTLD)
はじめに
疾患概念116
臨床症候の分類
bvFTD,SD,PNFAの画像所見
原発性進行性失語症(PPA)
FTLDの神経病理学的分類
FTLDトピックス
8. 高齢者の海馬硬化症~白くて小さい海馬の背景を探る
はじめに
認知症でやってくる高齢者の海馬硬化症~HS-Agingがある
HS-Agingの背景病理
HS-Agingの臨床
CARTS,LATE
HS-AgingをMRIで診断しましょう
第Ⅳ章 血管性認知症
1. 血管性認知症の多様な病態
はじめに
血管性認知症の診断基準
血管性認知症の分類
一過性全健忘(TGA)
第Ⅴ章 拡散強調像が鍵となる疾患
1. pathognomonicな信号異常が診断の端緒となりうる疾患・病態
はじめに
プリオン病
神経核内封入体病(NIID)
脆弱X関連振戦/ 失調症候群(FXTAS)
Hereditary diffuse leukoencephalopathy with spheroid(HDLS)
第Ⅵ章 積極的鑑別が必要な背景疾患
1. これだけは知っておきたい,その他の重要疾患
はじめに
高齢者の救急:認知症とのかかわり
“これだけは知っておきたい”理由は何か?
N:neoplasm(腫瘍性)
I :intoxication(中毒)
I :infection
M:metabolic(代謝性異常)
A:autoimmune(自己免疫性)
T :trauma(外傷と認知症)
老年期うつ病と認知症
第Ⅶ章 高齢者てんかんと認知症
1. 高齢者のてんかん
はじめに
日常画像診断でなすべきこと
第Ⅷ章 複合病理
1. 認知症の背景には複合的な病態が高率に存在する
はじめに
複合的な背景を診断するステップ
第Ⅸ章 社会とのかかわり~これからの画像診断の役割
1. 生活不活発病(フレイルとサルコペニア)
生活不活発病
フレイル(frailty)
サルコペニア
フレイル・サルコペニアの影響
フレイル・サルコペニアと画像診断
2. 虐待(abuse)
超高齢者社会における重要課題
3. 認知症と交通,運転免許
整備される法改正
4. ごみ屋敷症候群(別名:ディオゲネス症候群),熱中症など
ゴミ屋敷症候群とよばれる所以と背景要因
全文表示する
閉じる

●放射線画像×背景病理からわかる診断メルクマールのすべて●認知症マネジメントを見据えた画像診断レポートの書き方・読み方も分かる
年間1万例以上に及ぶ65歳以上高齢者の脳画像をみる神経放射線読影トップランナーが,汎用なCT・MRIから認知症の背景疾患の診断に迫る最前線のストラテジーを詳解。自験例を中心に認知症の背景疾患,注意すべき重畳的所見のなかでも特に優先すべき回復可能な疾患の鑑別から病期診断まで余すことなく徹底解説。新規治療薬で欠かせないARIAやピットフォールも豊富に示唆し,フォローアップ症例の病理画像やSPECT,解析データを交え,局所的診断と評価,根拠,放射線科医がチームとして共有すべき考え方を示す。認知症マネジメントに欠かせない日常診療の検査,高齢者診療にかかわるすべての人に伝える,放射線科医の視点からみた唯一無二のハイパーリファランス。